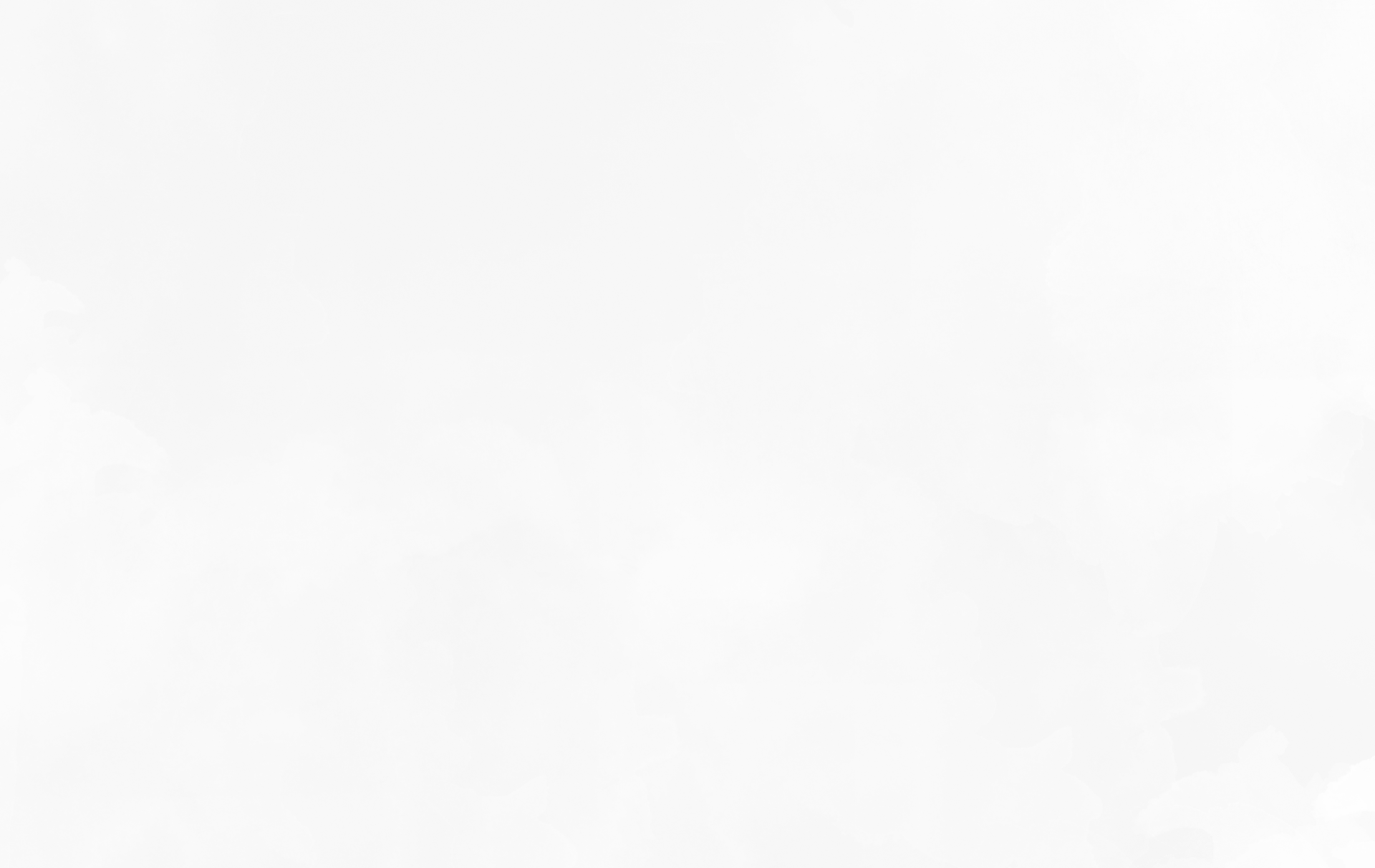
【ひと言】2022-1-12
【成城の名前の由来】
学園の名前の由来には中国の詩経(BC1046-BC771)の哲夫成城(賢い人が城を成す)と記載されていますが、以前から詩経には「哲夫成城哲婦傾城」という言葉があり、対句の意味が本来の意味にある。城が傾く哲婦とは(女性は政治を惑わす)という儒家の思想で女性蔑視の意味がある。 成城大学名誉教授の福光寛氏(証券市場論と財務管理論1998-2020)を担当され、この件で「哲夫成城」より、國語周語下(BC475-BC221)の「衆心成城」言い換えて「衆志成城」がふさわしいとの意見を発表されている。 一人の哲夫でなく、民主主義を構成する多様な人間をいかに育てるかが必要との意見がある。この意見には大賛成である。詳しく知りたい方は以下のレポートをご覧ください。 (16経D 遠藤洸一)
現代中国研究 : 哲夫成城か衆志成城か (livedoor.jp)
新規会員紹介

〇 山口裕哉自己紹介
はじめまして。35法Bの山口裕哉と申します。
成城大学法学部において4年間勉学に励み、先輩方や先生方のご助力のおかげもあって、幼いころからの夢であった弁護士業に従事することができております。
弁護士登録後は、ご縁もあって、埼玉県の法律事務所に勤務しておりましたが、昨年10月、地元である湘南地域に帰郷し、法律事務所を開設いたしました。
事務所運営及び日々の弁護士業という目まぐるしい日々の中で、成城大学での4年間をたびたび思い出しては、それを励みにしておりました。
そのような中、湘南成城会の存在を知り、成城大学出身の皆様とぜひ仲良くさせていただきたいと思い、この度加入させていただきました。
皆様と懇親を深めるのみならず、弁護士業という私の職業を通じてお世話になった成城大学や成城大学出身の皆様に恩返しができればと考えております。
若輩者ではございますが、皆様と良い関係を築いていけたらと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

〇 渡邉翔太自己紹介
はじめまして。35法Eの渡邉翔太と申します。
成城大学での学生生活を振り返ってみると、勉学や仕事に打ち込んだ日々は楽しい思い出ばかりかどれも貴重な経験でした。また、成城大学では一生の友人達に出会うことができました。特に先にご挨拶いたしました山口とは大学1年生からの付き合いで、藤沢市に共に法律事務所を開設いたしましたが、大学時代から将来は共に仕事をしようと約束をしておりました。このような人生を共に歩むことができる友人に出会えたのも成城大学のおかげだと感謝しております。
さて、私事ではございますが、沢山の方々に支えられ、今年で30歳という節目を迎えることができました。温かく迎えていただいた成城大学や湘南地域の皆様から受けた御恩を職業である法律に関することでお返しして参ります。
まだまだ至らぬ点が多く皆様にご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、末永いお付き合いのほど何卒よろしくお願いいたします。
2022年12月の声

【第54回成城学園同窓会講演会】
「スポーツビジネスの光と影 ~湘南ベルマーレの30年~」
【リアル講演参加感想】
私が平塚市に住むようになったのはJリーグ誕生の1992年、その翌年ベルマーレはJリーグ入りしました。天皇杯優勝、中田英寿選手の活躍などがあり、我が街にプロサッカーチームがあることは誇りでした。1992年、それが突然親会社の撤退により存続の危機・消滅の危機に陥りました。
真壁氏がベルマーレの社長に就任されたのは、まさにどん底時代のこの年でした。本日の真壁氏の講演を聴講していて、マーケティング講座の「ケーススタディ」を受講しているような錯覚が起きました。年商僅か7億円、年間3勝しか出来ない弱小球団を存続維持するための諸策。広告代理店を介さず、企業スポンサーに替わる650社の少額スポンサーの開拓、産能大におけるスポーツビジネス講座、楽しい・幸せ・豊かさをテーマにしたスポーツクラブの運営、そして若手選手の育成など多角的視野に立った数々の対策を伺いました。湘南ベルマーレのチームと共に、素晴らしい経営手腕を発揮された真壁氏が同窓生であることを、改めて誇りに思います。
(湘南成城会 15経C 山口俊彦)

【成城学園前の落葉掃き】
毎年恒例となった成城学園前のイチョウ並木の落葉掃き、今年は初日の作業に湘南を代表して遠藤会長と共に参加しました。まさに黄葉の真っ盛り、ハラハラと盛んに落葉が降りそそいで、車道歩道とも絨毯を敷き詰めたような落葉の風情は、これはそれで趣があるなと感じました。イチョウの葉は油分を含むので踏みつけると滑ります。近隣の住民にとっては迷惑なものでもあり、このためイチョウ並木の伐採対策が検討されたとか。慣れ親しんだ母校前の景観が大きく変わってしまう恐れがありました。そこで成城地区成城会が中心となってこの落葉掃きのボランティア活動が始まったそうです。
作業は約1時間、箒で集めテミで集めて袋詰め、大きな60㍑のポリ袋の山が出来上がりましたが、振り返ると相変わらずの落葉の絨毯状態、降りそそぐ落葉の勢いが止まらず、掃いたそばからまた落葉でした。この落葉掃きは火曜と土曜に合計6回続けられるとの事でした。
(15経C 山口俊彦)
【砧村から成城へ】
昔の砧村が今ではちょっと有名な「成城」へ。その頃のお話です。
私は昭和26年の成城高校卒業、来年3月で90歳になります。半世紀成城に暮らし、今は鎌倉(由比ガ浜~雪の下~現在は鎌倉山)に住んでいます。皆様ご存じの通り、昭和の始まりに東京は都心から拡がり小田急は西へ西へ新しい街を作りました。その中でも成城は学園都市として発展しました。住んだ人は、その頃の世界恐慌のきな臭さから帰国した人、芸術家達が多く住む町になりました。
1,600坪を4つに割り、一軒が400坪で全館が冷暖房の家が並び通りは真直ぐ十字に区切られていました。そこを成城学園に通う叔父が悪友のビリー(アメリカ人)とバイクで疾走していたとか…。絵描きの家を廻る裸婦のモデルさんが、「花は取ってもいいのよ」と、何処かの家から摘んだ花を一本持って私の家にも時々来たものです。
私の父親は高校からアメリカのシカゴ美術大学へ留学。その後フランスで絵を学んだ人で家には大きなアトリエがありました。“若い燕”と言う言葉を作った平塚らいてう(らいちょう)さんの家も駅の近くにあって、指輪やブローチを作るご主人の姿も生垣越しにチラチラと見え、夕方になると柳田邦夫さんが着物にステッキ姿で散歩される姿が毎日のように見られました。
夜、8時を過ぎると私の家には父のアメリカ、フランス時代の友人が東京から来て社交場となり、銀狐のコートを纏ったウィーンでピアノを学んだマダムや、有名無名のボンボン達がポーカーやチャールストンのステップで床を鳴らし、1920年代のジャズがステレオから奏でられる優雅な時間が流れていました。これは私が生まれて暫くの事で、私が物心ついた後に叔母達が昭和の良き時代を懐かしみ話してくれたのを耳にした事ですが、何故かジャズと言えば1920年代アメリカで流行ったメロディーが浮かんでくるのです。
むかしむかしのお話でした。 (3女A 松岡 弘子)
【老人力】
「伸びすれば足が攣る攣る寝起き前」シルバー川柳
そんな時は「ツムラ68」が効きますね。私の常備薬です。高齢者が集まれば先ず病気の話。そんな時友人が薦めてくれた本が「人はどう死ぬのか」久坂部羊著、講談社現代新書です。内容はかなりリアルに人が死ぬ時の様子が書かれていて、少々恐ろしくなりますが、無為な延命治療に警鐘を鳴らしていることには、納得しました。超高齢者の場合、救急車を呼ぶか否か?在宅医療のメリット等等、とても興味深く、参考になりました。皆様にも一読をお勧めします。
文中に印象的な言葉が2つありました。先ず1つは「Negative Capability」。これはジョン•キーツの言葉で、どうにもならない事へ対応できる能力のことです。このような能力が備わればいいな、と思います。2つ目は「老人力」。これは赤瀬川原平が提唱した概念で、年を取り全ての身体能力が衰えたことをネガティブにとらえず、「力」と呼ぶことで、年を取ることに積極性を与えることだそうです。
10月27日~29日、平均年齢78歳のクラレアメンバー8人で合宿を楽しみました。老人力を駆使して………。 (8文C 金子爽子)
2022年10月の声


【運動会の想い出】
終戦の翌年初等科から最後の女学校に上がりました。(翌年から新制中学校となる)
夏になると「皐月組」のおてんば数人、3時間目と4時間目の間の休み時間にお弁当を食べプールに。午後の授業はドライヤーのない時期、頭から水滴をたらしながらでした。
秋、大運動会はグランドの周りは生徒の椅子席、体育館の外側、段々席は父兄の方々。女学生は全員音楽に合わせ行進しながらSEIJOの人文字。旧制高校は絣の着物に袴、朴歯下駄のN氏率いる大太鼓を打ち鳴らしながら入場の応援団。ヤンヤの大拍手。またレースは四色(青、緑、黄、赤)の幼稚園から旧制高校までの抜きつ抜かれつ……何故かいつも黄色が優勝した記憶ありです。
高校の最後の時、何か変わったことをしようと「皐月組女子の棒倒し」を職員室に駆け込み談判、担任は臼井先生、さすが旧制第1回卒業生で、即OK。ただし「過激にはするなよな!」に「ハーイツ」、後で撮られた写真にはなかなかの雄姿でした。
卒業間近の職員室から「皐月組がいなくなったら淋しくなるなあ」との声が漏れてきたとか。「皐月」はお騒がせクラスでした。想い出がいっぱい、懐かしい成城は良かったなアでした。
私は中学低学年時代は水泳部、テニス部に。高校に上がった時はサッカーがしたくて「女子サッカー部」を作って欲しいと職員室に。残念ながら健康診断で「運動禁止」数名。2年の時一人男子の中に入れてもらいました。他校との練習試合にも2度程。 が今は左脚がしびれて歩くと痛みで杖をついての歩き。暴れすぎでバチが当たったかな?と思う今日この頃です。
(4女A 岩本麻里)
【鈴木重夫さんのコンサート】
10月1日、会員の鈴木重夫さんのコンサートがありました。会場は茅ケ崎駅南口を出てすぐのスタジオベルソウでした。
皆さまもご存知の通り鈴木さんは、昭和57年まで成城学園初等科の音楽専任講師をされていました。ピアニストであり作曲家です。
同業として交流の深かった故伊藤幹翁さんを偲んでのコンサートで、生前「先に死んだら残った方がお互いの曲を演奏しようと約束した」とのことで、伊藤幹翁さん作曲の童謡が4曲ソプラノ独唱で演奏されました。あとはすべて鈴木さんの作曲・編曲のもので、歌手が歌い、ピアノ連弾ではご本人の演奏もありました。80歳を過ぎると指が動かなくなると話されていましたが、何のその、立派なテクニックに感動です。明るく軽快な曲、しっとり聴かせる曲、詩に合わせて自由に音を操る作曲家の幅の広さにも感激ひとしおでした。
(12短A 山口和子)

【人生の扉】
2007年に竹内まりや自作自演の楽曲【人生の扉】の歌詞が、まさに我々人生そのものを唄っています。
この楽曲をご存じの方ももう一度、耳を傾けてみたらいかがでしょう。
参考のために歌詞全文を紹介します。
春がまた来るたび ひとつ歳を重ね
目に映る景色も 少しずつ変わるよ
陽気にはしゃいでた 幼い日は遠く
気がつけば五十路を 越えた私がいる
信じられない速さで 時は過ぎ去ると 知ってしまったら
どんな小さなことも 覚えていたいと 心が言ったよ
I say it’s fun to be 20
You say it’s great to be 30
And they say it’s lovely to be 40
But I feel it’s nice to be 50
満開の桜や 色づく山の紅葉を
この先いったい何度 見ることになるだろう
ひとつひとつ 人生の扉を開けては 感じるその重さ
ひとりひとり 愛する人たちのために 生きてゆきたいよ
I say it’s fine to be 60
You say it’s alright to be 70
And they say still good to be 80
But I’ll maybe live over 90
君のデニムの青が あせてゆくほど 味わい増すように
長い旅路の果てに 輝く何かが 誰にでもあるさ
I say it’s sad to get weak
You say it’s hard to get older
And they say that life has no meaning
But I still believe it’s worth living
But I still believe it’s worth living
人生の扉を開くと【過去】と【未来】を思い描き、【現在】の自分の人生と重ね、今まで以上に
時間を大切に使わねばならないと思います。
you tube等でこの【人生の扉】の楽曲をお聴きになってみてはいかがでしょう。 【岩佐福之】

2022年11月の声
2022年5月の声
【青春の思い出…水球で日本一】
私の成城大学在籍中は、諸先輩に恵まれ、昭和33年(1958年)9月の日本学生選手権(インカレ)水球競技大会で、日本大学を破って成城大学が優勝し大学日本一になることが出来ました。
当時私は、京都の山城高校を卒業して成城大学に入学した1年生でした。当時の水泳部監督な、旧制高校21理乙(昭和24年)卒業の村瀬友三郎様でした。そして、大学4年生には新制高校7新高(昭和30年)卒業の阿部武彦様・堀正美様・山本勉様という諸先輩がおられ、その中に京都の山城高校から入学した私達が入り乱れての最強チームでした。
新聞掲載にあるように昭和33年のインカレは、当時最強チームと言われた日本大学を破っての優勝で「金メダル」を獲得したのです。私の一生の宝です。この紙面を借りて、諸先輩方に御礼を申し上げたいと思います。
昭和33年9月8日 毎日新聞
成城大学卒業後は、社会人チームに入り昭和38年にインドネシアのスカルノ大統領が開催した「新興国スポーツ大会」(ガネホと言い51ヶ国、2,700人が参加した国際大会)に出場して「銀メダル」を獲得しました。 (10経B 村上 (旧姓 本郷) 順三)


【TVの追悼番組を見て】
この2年有余、趣味のコンサート観賞も思うにまかせず、またトリオでの老人施設へのボランティア演奏活動も、感染防止のため一切行うことも出来ず、自分史的には空虚空白の月日であった。しかし半月ほど前、TV・WOWOWが世界3大テノール歌手のひとりルチアーノ・パヴァロッティの追悼番組歌劇「トゥーランドット」ミラノ座の公演録画が放映された。ステージは「誰も寝てはならぬ」が唄われる前に万雷の拍手でカーテンコール、それでも久しぶりに心晴れやかな良きひと時を過ごすことが出来た。生前の妻から「3大テノールの内誰が一番好きか」と問われ、私はパヴァロッティと答え、妻は「ホセ・カレーラスよ。何故なら私と同じ病と闘っているから」と。この数年後、妻の希望通り音楽葬、フォーレのレクイエム「ピエ・イエズス」とドビュッシーの「アラベスク」。真っ白なカーネーションとバラの花に包まれて天国へ。15年の歳月が過ぎました。
他方世界最高峰の歌い手であるパヴァロッティは母国イタリアでの冬季オリンピックの開会式で唄ってから程なく、世界中の人から惜しまれつつ天国に旅立ってから奇しくも15年………。あれやこれや往時が思い浮かんできます。
今現在はコロナの鎮静化、ウクライナの自由と平和を勝ち取る願いと、大谷君のホームランと勝ち星を日々期待しています。 (10経E 三澤一雄)
2022年4月の声

【ウクライナ避難民、受け入れの事】
去る2月24日ロシア軍のウクライナ侵攻が始まった事を知ったとき、私は”まさか!”という思いであった。
1991年から10年余、私はモスクワを起点にして旧ソ連の国々で 茶道の普及活動を続けてきた。その中で、ウクライナには何度も訪問して茶道の活動をしてきた。自然ロシアとウクライナ両国の人々が、どのような関係にあるかについて知ることになった。
この二か国は、当に親子、兄弟、親戚と言った濃い血で繋がった人々が、無理矢理に作られた国境によって分けられているだけのことで、本来両国の個々の人々の間には、割いても割けない深い関係が歴然として続いているのである。そんな中で、片方が一方的に暴力で相手を殺したり、家を破壊するなど、常軌を逸しているとしか言いようがないのが今回の戦争である。
実際私には、どちらの国にも少なからず茶道の生徒が育っている。当然彼らは国境を越えた兄弟弟子として深い絆で繋がっており、私との関係も続いて来ている。それで今回の現実を知ってからの私は、何をどのように考えて良いのか、しばし思考が止まった。何とも言い様の無い苦しい思いをすることになった。それでも何とか思考を働かせてみると、両国の生徒たちは現在生きている場所が大きく違ってはいるが、その戦乱に対する基本的な考え方は、皆私と同じであることに疑う余地はなかった。そして彼らは、現実の出来事の中で、それぞれが懸命に自己の想いに向き合っているということに気がついた。
その現実は、ロシアの生徒達はウクライナの仲間の安全を想って深い悲しみと共に、ロシア人であることを恥じて苦しんでおり、一方、ウクライナの生徒達は、家族と共に、お茶の友人達の身の安全を考え、必死に生きようと努力している、のである。そんな事に気が付いた私は、つい涙が出てしまった。そして、今私に何か出来る事は無いか、と考えるようになっていった。
そこへ、岸田総理が国会で、ウクライナの難民を日本に受け入れることを表明し、次いで大臣のポ-ラント出張と、帰路の飛行機に避難民を乗せることが明らかになった。その頃、ポ-ランドに避難していた生徒の一人、が子供と共に来日を希望していることが判明し、私としてしはなんとかその二人を、その飛行機に乗せてもらえるよう、関係機関への働きかけを開始。同時に、来日後の生活を始める準備にも着手。忙しい毎日が始まった。そして、関係者のご理解を得て4月5日二人は羽田空港に無事到着、今では鎌倉市内のアパ-トで日本の生活に順応しようと努力して頑張っている。まだ言葉の壁も高く、自立するには日を要しようが、いずれ自力で生活できるよう、私としては支援を続けている。
しかし、ウクライナでもロシアでも、沢山の生徒達が日々の生活の事だけでなく、深い心の痛みに耐えて頑張って居る。支援はまだ始まったばかりだと思っている。
(15経F 西川 勝 茶道教授)
【韓国ドラマのファンになった】
昨年偶然チャンネル銀河で韓国歴史ドラマ(伝説の心医ホジュン)を見て韓国歴史ドラマのフアンになってしまった。続けて(チャングムの誓い、イサン、トンイ)と午後2時半から4時までテレビの前に釘付け。話の進行がスピードがあり話そのものがまるでプロレスのような面白さなので飽きがこない。サーベルを振りかざしてリングに上がるタイガージェットシンとアントニオ猪木の戦いのようである。プロレス同様善悪の問題ではないのだがそこはドラマ。主人公が危機に瀕すれば画面に釘付けという状態。更に俳優が素晴らしい。体格体型が日本人と大分違い見ていてその所作と合わせ非常に気持ちが良い。ドラマによって俳優が悪役をやったり善人役をやったりする。どの役者も悪役をやった方が上手い。韓国の俳優は口元が上品な人が多い。特に(イサン)に出演したハンジミンは口を開くと小粒の真珠を並べたような歯並をしている。ほれぼれしてしまう。三十数年前に韓国旅行をしてから韓国に興味を持っている。とにかくやることが日本と違う面が多く興味の尽きない国である。また行ってみたい。 (10経 平子邦雄)

【“幸せ”は人それぞれ】
漫画家のヤマザキマリさんのエッセイがJAFMate春号に掲載されていました。
素敵な内容なので、皆さんにも一読してほしくてこの会報に紹介します。
“幸せ”は人それぞれ (ヤマザキマリ)
漫画がヒットした頃、出会う人々から「ヤマザキさん、嬉しいでしょう。幸せでしょう」
とよく言われることがあった.。確かに世間的な尺度で捉えれば、漫画のヒットも海外暮らしも“幸せ”の一般条件を満たすものかもしれない。しかしこうした“幸せ”の感覚がすべて万人に共有できるものかと言うと、それは違う。
(中略)
面白い本や映画に出会えた時、大好きな音楽を聴いている時、友人と気兼ねなくお喋りしている時、日当たりの良い場所で寝ている猫の顔を見ている時、地面に立派な根を張り、枝いっぱいに葉を生い茂らせている木々のの間を歩いている時、抜けるような青空を見上げる時、海に潜っている時、旅の先々で地球を美しい惑星だと感じる時、そんな時、私はたとえ「死」という前提があっても、命を授かって良かったと思う。束の間であってもこの地球という惑星に生息するという体験が出来てよかったな、と感じる。
この世には、家族や帰る家のあることこそ幸せだと捉える人もいれば、束縛のない自由奔放な風来坊的暮らしが幸せだと感じる人もいる。戦火から逃れ、命があるだけで究極の幸せを感じる人もいる。生きることに挫けないために人間がそれぞれ生み出す“幸せ”は、果てしなく多様であり、そしてその価値感は、押しつけるものでもなければ、押しつけられるものでもないのである。
以上がヤマザキさんの書かれた内容の抜粋です。
さて自分の“幸せ”とはなんだろうと考えてみるに、何が言えるでしょうか?_
「満足すること=悩み、苦しみや不満がなくなる」ことかな?
そのためには煩悩が消えれば不満がなくなる。煩悩はすべての人が持っている「勘違い(かんちがい」からくるのだと言ってもいいのかもしれません。
「あッ、それって勘違いだったんだ」といえるようになれば、不満が消えて満足出来ることにつながるのではないかと思います。つまり、どんな状況や場面にあっても、煩悩をけして、慌てずにじっくり見つめて生きる事が“幸せ”につながると思いますがいかがでしょう。 (10経 岩佐 福之)

【ムーリエ】
小学生の時に羽田空港に遠足に行った。初めて見る飛行機はもちろんプロペラ。その時は夢の乗り物で、自分が乗るとは想像がつかなかった。社会人になって、いろんな飛行機に乗ったがA380を見たときその大きさに驚いた。さらに世界最大のウクライナのアントノフ225はいつか見たいと思っていたが残念ながらロシアの攻撃で破壊�された。またいつか再建してその勇姿を見たいものである。 ムーリエはウクライナ語で夢(Dream)というらしい。飛行機ファンの夢を壊した戦争の無意味さと平和の大切さを痛感しています。 (山口 俊彦)

2022年3月の声
【実家の家じまい】 (22経B 加藤幸佐)
2021年11月26日、築150年以上も前に建てた母屋の裏にある蔵屋敷を含め三重県の実家じまいを、約3年間かけて終了しました。本来なら昨年中に実家の引き渡しが完了していたはずが、コロナ感染拡大の影響で一年のびのびになり、やっと終了しました。
実家の処分は「売却」でなく、「贈与」でのかたちを選びました。この文章を読んでくれる皆様の大半は6年前に「伊勢・志摩・熊野」の旅行に参加した人も多いと思いますが、私の古い実家も覚えていてくれていると思います。私自身実家での生活は15歳まででしたが、社会人になってからも年に一度は必ず帰省していました。
特に親父が20年以上前に他界してからは、大阪への出張帰りに時々帰省し、年老いたお袋が一人で生活している様子をうかがいながら、実家に1泊し藤沢に帰ってきました。私自身60歳で会社をリタイヤーした後も、実家の処分についてもまだ先でもいいとの考えでおり、当時はお袋も元気で一人暮らしをしており、私自身リタイヤー後は時間もあり時々実家に帰っていました。その後、お袋が2度も骨折し、入退院と施設での生活を繰り返し、実家での一人生活は困難と判断し、今年で老人施設に入居して8年になり、幸いなことに現在96歳です。8年前から、親も住んでいない実家に帰省し部屋に風をいれたり、庭の掃除をしたりするだけの帰省が始まり、さらに藤沢から、三重県までの遠距離運転もいささか、しんどくなってきました。65歳ごろから本格的に実家の処分を考え始めるようになり、伊勢市の不動産屋さんに相談し、どのような処分方法がいいのか検討始めました。
売却するには田舎の過疎地であり、さらに家屋が老朽化しており、値段がつかない。更地にして売却するにしても5,6百万円以上の解体費用がかかるとの見積もりが出ました。又、約200坪の土地を解体して更地にしても買主が見つかる可能性も低いとの結論でした。土地所有者でも都会と過疎地では雲泥の差、まさに格差の典型的な事例です。
ところが2年半ほど前にある人の紹介で私の実家に興味があり、一度家の中を見させてほしいとの話があり、蔵の中とか、蔵の中にある古い書物・古道具類、家の隣にある古い郵便局舎の建物にも興味をもっていただいて、2回目の面談の時、将来的には実家を処分したいとの考え方に対し、それなら譲り受けたいとの申し入れがあり、本来なら、昨年の初め頃から、具体的なスケジュールを話し合う予定でしたが、コロナの影響で私自身三重県に帰れなくなり、昨年中は一時中断するも、今年に入り 感染拡大時期を避け、実家に帰省するときは当然PCRの検査を受けてから帰省し、無事実家の引き渡しを完了しました。
先方の知り合いの司法書士さんを介して贈与契約を結びましたが、さすがに家の権利書を渡し、書面にサインをしたときはほっとしたと同時に複雑な気持ちにかられ、先祖代々から続いている実家を私の代で終わらすと思うと、親父の顔が浮かび申し訳ない気持ちにかられました。東京から遠く離れた三重県の田舎の実家を残せば、将来息子にも苦労かけるとの思いから選択をしたわけであり、今は最良の選択をしたと自分自身に納得させています。
お墓は当分三重県に残しますが、実家を引き渡すのに際し、仏壇の魂抜きを住職にお願いし行いました。
実家を引き渡すに際し、先方さんは生活していた衣類・布団関連以外は「居抜き」の状態で構わないとのことでしたが、10月、11月と2回に分け家の中の整理をしました。50年以上前から、タンスの引き出しに大事にしまっていた着物類も躊躇なくごみ袋に入れあっけないものでした。管理50年処分5秒。人生もそのようにはかないものなんでしょうかね。その中で、蔵屋敷の2階のタンスの中から、70年前の両親の結婚式の写真が出てきました。私も初めて見る写真です。人間ていうものは大事なものは大切に保管しているなあと改めて感心しました。
だんだん痴ほうが進んでいる母ですが、私の妹が年末に施設に面会に行くとき写真を持参するので、その反応がたのしみです。
大学を卒業するとき教科書や書物類を実家に送ったままの段ボール箱がそのまま保管されてました。押入れの奥の段ボールを開けると,湿気のせいで、本が腐っていて開けない状態でした。本も可哀そうに50年近くそのままの状態で保管されてました。フロイトの「精神分析入門」、エリッヒフロムの「自由からの逃走」、松坂ゼミの「ケインズ経済」当時新進気鋭の社会学者の石川弘義先生の「欲望の戦後史」等懐かしい本が出てきました。石川先生は上田君と一緒に入っていたゼミのフロイト研究会の先生でした。石川先生は今から50年以上も前に「人間の欲望」というテーマで本をかいたり、TVに出演していました。 今の社会風潮を先取りしていたのでしょう。高度経済成長で3種の神器をはじめ、物質文化を謳歌し益々社会生活が向上し、人々が豊になっていく社会を予見していたのはさすがですが、先生が生きていれば、今の社会をどのような眼で論評したのか聞いてみたいですね。フロイトと同じように、心の病を指摘していたかもしれません。
もう一冊本が出てきました。ある社会学者の「宇宙船地球号」という書物です。本人来日した時、私自身講演を聞きに行きました。これも50年以上前のことです。地球は宇宙の一つの星であり、今、世界中は物の生産を続け、成長を続けているが、その結果当然ゴミが地球のどこかで溢れてきて社会問題化する。本を書いてから60年以上たちますが、60年後の世界に対しての警告書だったのです。当時東京もゴミ戦争がすでに勃発していて、江東区の夢の島にゴミの埋め立て地の建設でもめており、世田谷の砧に新しいゴミ清掃工場の建設で住民の反対運動が盛んにおこなわれており、私自身夢の島も砧のごみ焼却炉の見学にも行きました。
松下電器の入社試験の面談で入社したい動機を聞かれたとき、人間の欲望の部分を家電製品の普及に努めたい、しかし、世界中は今後もゴミ問題で悩まされていく、住民同士のトラブルも多くなっていく。自分自身、両方の部分を解決できるような仕事をしたい。面談ではそのような内容のことを話したように記憶しています。いまは世界中は環境問題。脱石油。脱炭素。今後どのような世界になっていくのでしょうね。
実家の家じまいを契機に、70年の人生を振り返る良い機会を得ました。それでも、今でも今回の選択は最良の選択だったのかと、自問自答しています。世間の人は三重県の伊勢志摩は風光明媚でいいところでしょうと、人は言います。しかし現実には、過疎地で、撲滅集落と呼ばれ、国も助けてくれない、行政の援助もなく新たな産業もなく、町全体がさらに衰退していくであろう姿を私は想像できます。
幸いなことに実家を譲り受けてくれる人はそのような地域であり、実家の実態を承知の上、譲り受けてくれました。 本人は家の中の痛んでいる箇所を2,3年かけてリフォームしたいと構想を練っています。私自身も実家がどのように生まれ変わるのか楽しみにしています。
加藤家の話になりますが、長男は昨年秋に約5年間駐在していた、中東のカタールから、日本に帰って来て、今年になって、今回3回目ですが、同じく中東のドバイ・アブダビに現在出張中です。オミクロン株の騒ぎで一時帰国できないかと心配しましたが、今後大きく状況に変化がなければ、年末までに帰国できそうです。やはり、海外勤務が多い長男に田舎の実家を残すという選択はなかったです。
念願であった、実家の家じまいが終わり、残された人生を有意義に目標を持ち、どのように生き抜いていこうかと、改めて考えてゆきたいと思います。
皆さんはどのような目標を立て生き抜こうとしていますか?あと10年?20年?いや30年かなあ。


2021年11月の声



【学友は人生の友に】
山梨県の東部、山間部を縫って相模湖に注ぐ秋山川のせせらぎが聞こえる「過疎」の中学校、3年生の教室。私の担任の近藤先生は、「将来、大学に行くなら」と言いながら、黒板に「成城」「成蹊」と書き、以下のような説明をした。
「成城は、中国の古典から「哲夫城を成す」から採られている。哲夫とは、哲士、見識の優れた人という意味。城は国のこと 。他方、成蹊は、史記の「桃李不言 下自成蹊」から来ている。どちらの大学も、少人数のため教授が親切で、自由に勉強するには、良い学校と思う」と。
1970年4月、新入生は、成城学園の「哲士寮」で合宿した翌日、経済学部長からクラス委員指名と訓示があった。私は、1年A組のクラス委員に指名されたが、昨晩懇親した学友も何故私なのか、昨晩の会話からは意外であり訳が分からなかった。
授業が始まり、経済学の上野教授から「苦海浄土わが水俣病」(石牟礼道子著)を勧められた。工場から流出した有機水銀が、身体にもたらした悲惨な病状が描かれていた。 今日「ESG」投資や「SDGs経営」の必要性が、全世界で求められています。地球環境維持に配慮した市場経済の進展を期待せざるを得ない状況と考えます。
2年になると、先生は、「デヴィット・リカード」の「経済学および課税の原理」をテキストに採用しました。私は、今になって思うと「比較生産費の原則」は、今でもグローバル経済の基本理念になっていると思っています。
授業以外では、新聞会に所属しましたが、3年になった時、経済学部会総務を務めました。執行部として、妹尾理事長や松坂経済学部長と面談する機会がありましたので、お考えをお聴きし、大変勉強になりました。
4年生では、教育実習で出身中学にお邪魔しました。
社会科担当指導教諭が「人生は、清く、正しく。美しく、地位も、名誉も、お金もいりません」と飲み会で話されたので、当学園の「真・善・美」ですね、と賛同しました。十分楽しんで大学に戻ったところ、「こんな高い成績の評価は見たことがない」と教育実習担当の教授がびっくりなさったので、「私の中学校の成績と同じですね」とユーモアでお応えしたら、「母校に行かせると評価が、甘い傾向があるが、それにしても・・」と笑顔で仰られました。
卒業後、私は、38年間、証券界に勤務しました。退職率が高い業界でしたが、仕事が飽きて嫌になったことはありませんでした。「諸行無常」や「ゆく河の流れは、絶えずして、しかも、もとの水にあらず」が好きでしたので、職種が性格にあっていたのでしょうか。
勤務が首都圏の間は、上野ゼミOBによる懇親会が楽しみで、可能な限り、参加しました。ある日の会合で、「関戸」という名字をお知りでしたか、と先生に尋ねたら、「若いころ八王子のコーラスグループに同姓の方がいた。企業経営で成功した方だ」とのお答えでした。その方は、「私の母方の血族です」と言うと、先生は、驚かれました。私は、先生との不思議な縁に気付いて、他校にはない成城ならではの師弟関係を発見して嬉しい限りでした。
他校にないといえば、卒年によるハッピイバースデーの祝賀会もありました。2015年5月、1974年卒(22経済)が当番年次でした。実は、この会場で「湘南成城会」の看板が目につき、ブースに近寄った所、現事務局の山口俊彦さんの奥様である和子さんのにこやかな笑顔に出会いました。なんとなく、その場の雰囲気で、同年次の加藤さんとその場で入会を承諾してしまいました。その後、趣味のゴルフ分科会に入会しました。今は、ゴルフ分科会の幹事を務めています。(中断していますがBBQの幹事も数回やりました)
また、哲士寮を皮切りに知り合った学友の十数人とは、各自の実家や出身地観光を行っていましたが、昨今のコロナ対応で、旅行は中断して、「グループライン」や「オンライン懇親会」を通じて、近況報告や健康相談及び意見交換をしています。
振り返ると、同年次の学友とは、半世紀の交流が続いています。ひょっとしたら、親や妻よりも、たくさん意思疎通しているかもしれません。住居は、1983年から、妻が茅ヶ崎市の小学校教諭でしたので、辻堂駅から西に徒歩7分に住み着き、現在、息子夫妻と孫2人と「湘南茅ヶ崎」で暮らしています。「湘南成城会というネームは、好感度が高いネームとですね」というお声を頂きます。古希を超えた私たちの年次の交流は、学友から「人生の友」に昇華していくように思います。
ましてや、年次を超えた親睦の輪である「湘南成城会」での活動が、名実ともに、各々にとって人生の潤いとなることを祈念して、「巻頭言」とさせていただきたく思います。 (湘南成城会 副会長 関戸豊明)
【コロナ禍の生活】
コロナ発生以来はや20数ヶ月、私の日常はがらりと変わってしまい、仕事としていたピアノレッスン、コーラス指導、歌声の会、シャンソンの会などことごとくキャンセルとなってしまいました。音楽活動が今までのようになってと願うばかり。
以下はそのコロナ禍の中での出来事を日記風に綴ってみました。ご笑読下さい。
車の免許証を昨年暮れ返上。(高齢者の事故を見聞すること多くなり)晩節を汚してはいけないと思い返上した次第。(でも未練たらたら) また自転車に乗ることも。よって歩くこと多くなり、自宅から海に向かって散歩。また鎌倉山、二宮の吾妻山数度散歩。鎌倉山ではオニヤンマとそのヤゴ、せせらぎを泳ぐマムシ、鳥のさえずりなど散見。
地方(新潟、金沢、相模原など)から送られてくる同人誌に目を通すこと今までより多く、その結果気に入った作品に付曲し作者に返送。大変喜ばれる。嬉しいことが8月に。愛知県で行われた“きらめきピアノコンクールで私の作曲した連弾曲 “The Rumba Samba” が優秀賞を受賞。
恐る恐る東京に出かけ、コンサートや絵画展の観賞と鑑賞。葉山の県立美術館での絵画展、鎌倉での鎌倉彫刻展、芸術劇場での第九コンサート、代々木の白寿ホールでのシューマン・チクルスコンサート、文化村でのシャンソン“パリ祭”、紀尾井ホール、玉川区民会館での自作品発表コンサート。三軒茶屋での歌曲のコンサート。
珍しいことが2件ほど。昨年の12月17日に自宅のベランダに動かないカゲロウが。触ってみたらなんと羽をばたつかせる、室内に入れたら飛び回る、でも翌朝にはご臨終、合掌。今年6月12日には実に鮮やかなマゼンタ色の朝顔は咲き始めビックリ。
7月1日に2回目のワクチン接種終了、めでたしめでたし! 10月4日実に久しぶり「歌声の会」。通常160~180名の参加者を40名に抑えて再開。続いて緊急事態宣言明けの藤沢の朝市。香川のIMOKICHIに買い物と食事。22日新宿武蔵野館でルネ・クレールの映画作品に出かける…用心して。特筆すべきこと、ウナギを食することコロナ禍でなんと8回。
駄文を読んでくださりありがとうございました。 (元初等科音楽講師 鈴木重夫)

【イノシシの話】
趣味で15年ほど畑をしています。場所は大磯の吉田茂邸や城山公園の裏側にあたる運動公園の前です。ほぼ三方に山を背負った扇状地の一番下の県道に面した場所です。土地の持ち主が病気で耕作できず荒地になっていた所を頼まれて畑にしています。
昨年の6月のことでした。収穫直前のジャガイモ、植えたばかりのサトイモ、ヤマイモなど見るも無残にイノシシに食い荒らされました。荒れ果てた酷い有様にしばし言葉もなく呆然としました。「もうヤメタ」と一時は思う程のショックでしたが、ソーラー発電の電気柵を設置して続けています。
私の隣の畑で、やはり被害を受けた人が大磯町役場勤務でした。幸運なことに今年4月の異動で「害獣駆除担当課長」になり、早速捕獲用の檻を設置することになりました。
鋼鉄製の頑丈な檻で、中央に米ヌカを山盛りにしてあります。そのすぐ上にピアノ線が張られて触れるとフックが外れて扉が落ちてくる仕掛けです。「まだかまだか」と期待して通うこと1ヶ月の8月11日、ついに1頭立派なヤツが捕獲出来ました。
ところがその後わずか3日後、真新しい足跡がそこら中に残り、小さな足跡も混ざっていて子連れだと分かりました。仕掛けを整備し直して待っていると8月28日でした。なんと檻一杯に親子のイノシシがひしめいていました。即座には数の把握が出来ない程です。親メスが2頭、子(ウリボウ)が6頭の計8頭でした。
イノシシはオスは単独行動、メスは複数で共同で子育てするそうで、最初に捕獲されたのはオスだったようです。想像ですが、最初に子イノシシが檻に入り、それを見て親も入って来て「一網打尽」となったのでは。撮影した動画を良く見ると、1頭だけ檻に入りそこなったウリボウがいます。とても幼そうなので親なしでは生き残れないだろうとのことです。
それにしても一つの檻で一度に8頭も捕獲されるのはめったにないことと話題なっています。大磯町で今年の8月までの捕獲数は30頭とのこと、私の畑だけで9頭の実績です。自慢して良いのやら複雑な心境であります。 (15経C 山口俊彦)


【ヒマラヤの青いケシ】
海抜8000メートル級の白く輝くヒマラヤの山麓、海抜4000~5000メートルの薄い大気と強烈な紫外線を受けて咲く天上の妖精、幻の青いケシ。ブータン王国の国花に指定されています。
箱根湿生花園で咲き始めたとの情報を得て鑑賞して来ました。耐暑性が非常に弱く、低地では咲いても色があまり青くならないとか。鉢植えで6株ほどが展示されていました。
本来ならば箱根研究会の行事として企画するところでしたが、コロナ禍で今回は断念しました。来年こそは……。 (山口 和子)

【米国における同時多発テロから20年】
映画のワンシーンではないかと思うようなTV画面を見た時から早いものでもう20年が過ぎました。通算10年半の米国駐在から帰国して既に4年が経っていました。刻々と映し出される現場の悲惨な状況。何が起こったのだろうか想像するのにかなりの時間が必要でした。
その頃、家内の両親は南カリフォルニアに住む長男家族を訪ねようとロスアンゼルスに向かう飛行機に搭乗していました。TVからは色々な情報が立て続けて流れてきて、主要空港は更なるテロを警戒して閉鎖されたとのこと。その中にロスアンゼルス国際空港も含まれていました。 今まさに太平洋上をロスアンゼルスに向かって飛んでいる義理の両親が乗っている飛行機はどこに向かうことが出来るのか。南カリフォルニアに住む義理の弟と連絡が取れ、その飛行機はロスに着陸できないのでサンフランシスコに向かうことになったと知らせてきました。そして今から車でシスコまで迎えに行くとのこと。相当時間はかかるだろうが他に選択肢はないので頑張って行って欲しいと妻は受話器を持ちながら頼んでいました。
同時多発テロのTV中継はその後テロにあった各地の様子を映しだしていましたが、正直なところその映像を見続けるのが辛くなりました。このようなことが何故起こるのだろうか、何故人間はこうも残忍なことをやれるのだろうか。そのようなことが頭の中をぐるぐる駆け巡っていました。
義理の両親を乗せた飛行機はその後無事シスコに着陸し、全てのエネルギーを使い果たして遠路はるばる車を飛ばしてきた長男と無事会うことが出来ました。
(小保方健)



【私にとってのコロナ渦】
我が家では、二男家族がアメリカ西海岸のハンティントンビーチに、長女家族はオーストラリアのシドニー郊外に暮らしています。2019年の夏には、毎年の慣例通り両家族が帰省し9才から3才まで合計4人の孫達、息子夫婦、娘夫婦、そして辻堂在住の長男夫婦共に賑やかな夏を過ごしました。それまでは、年に1~2度こちらから彼等を訪ねることもあり、インターネットでのビデオ通話も頻繁に出来るので、離れて暮らしていることの寂しさを、それほど深刻にとらえたことはありませんでした。
2020年に入り、新型コロナウィルス感染症によって、予想もしていなかったことが次々に起こり、先ずはアメリカでのパンデミックの報道を目にするたび耳にするたびに、二男家族のことを心配し、オーストラリアは世界の中でも感染者数がおさえられていたとは言え、娘夫婦がレストラン事業を開業して間もなくのロックダウン、日本に比べると迅速で手厚い政府の補助を受けながらも、仕事の先行き不安に加えて、春先には2人目妊娠の報告を受け、本当ならヘルプに飛んでいくはずが、日本でもゴールデンウィーク前からの緊急事態宣言で身動きとれず。 夏になっても孫達の声がまったくしない静かな毎日を過ごし、秋には17年間共に過ごした愛犬を見送り、年末に出産を控えた娘の所へ行けることをひたすら願っていましたが、もちろん叶いませんでした。
コロナ渦での出産に際して、病院には家族1名のみの同行が認められていましたが、「じゃ、4才になったばかりの上の子はどうするの?」「夜中におなか痛くなったらどうする?」「上の子の時のように難産だったら…」心配事山積みでしたが、娘はなんともたくましく第2子を出産、しかも結局帝王切開、そしてまさかの3日目で退院。さすがに退院後1週間ほどは有給のヘルパーさんに通って頂きなんとか乗り切ってくれました。退院後の様子もビデオ通話で知ることが出来たので、少しはホットできましたが、生まれたての5人目の孫をこの手で抱いてあげることができないまま、そして今年もまた2度目の静かな静かな夏を迎えたのでした。アメリカの二男家族も、2020年早々に始まったパンデミックで、仕事はもちろん学校もすべてオンライン、遊び盛りの3人の男の子達が友だちにも会えず、大好きだったスケボーもBMXもできず約1年半、ようやくこの9月の新学期から学校に行けるようになったそうです。
それにしても、それぞれに窮屈な制限を受け、感染対策に気を配り、ストレス満載の日々を過ごしながらも、今日まで家族の誰一人感染すること無く、元気に過ごしていられることをありがたく思いながら、家族が海外に暮らしていると言うことの現実を改めて思い知らされたのが、私のコロナ渦です。
昨年末に生まれた孫を、「まだプニュプニュのうちに触りたい、抱っこしたい、頬ずりしたい」と願い続けていますが、早くも10ヶ月を過ぎてしまい、つかまり立ちを始めています。つい数日前(10月中旬現在)、オーストラリアのモリスン首相が、「NSW州民のワクチン接種率が80%を越え間もなく90%に達するので、海外からの入国及び隔離条件を段階的に解除していく予定で、永住者の海外からの家族はワクチン接種済みで陰性であれば、隔離無しで入国できる日も近い。」と発表しました。飛んでいきたい!毎日、更に情報が更新されるのを心待ちにしています。
(16文D 相澤千春)


2021-4月・5月会員の投稿


【Boys be ambitious】
世の中には若い人々の指針になるような言葉がありますが、中には問題のある言葉もあります。本日は、かの有名なクラーク博士の言葉を考えてみたいと思います。
「題」は(Boys, be ambitious like this old man)です。
一般にはlike this old man)はなしの(Boys, be ambitious)と言われていますが、この点については後述します。「少年よ大志を抱け」と言うこの言葉は有名ですが,クラーク博士の言葉の内容は果たして「少年よ、・・・」と言う意味であったのかどうかを、検証します。
第一に「大志」と言う言葉の意味が分かりません。最新版の広辞苑で「大志」を調べたところ「大いなる志」と説明されています。この説明では意味が分かりません。
ならば、英文から意味を探っていきたいと思います。
まず(boys)です。この言葉が語られた場面は、クラーク博士が1年間の日本滞在を終え離日する際、見送りに来ていた札幌農学校の生徒に馬上から語られた言葉であると言われています。博士は(Boys, be ambitious like this old man)と語ったとされています。
ならば(boys)は「少年よ」ではありません。札幌農学校は男子校です。見送りに来たのは全部男子生徒です。だから(boys)と語り掛けたのです。この(boys,…)は見送りに来た生徒たちに、向かって発せられた言葉で、「諸君」と言うのが正しい答えです・
「少年よ、大志を抱け」と言った人物は、(boys, be ambitious)に違う意味の言葉を付けたのです。
語られた時の状況を度外視して、「少年よ」と言ってしまうと、日本はもとより、全世界の少年に向かって発せられた言葉になってしまいます。
さらに言えば,この世の中には少年とほぼ同数の少女がおります。「少年よ」と言ったのであれば、「大志を抱く」のは少年だけになってしまい、少女を無視したことになります。
熱心なキリスト教徒であった博士が少女たちを無視することは考えられません。したがって、語られた状況から、(Boys)は「少年よ」ではなく、「諸君」が正解でしよう。
次に(be)です。
命令文においては(be)は「何々であれ」「何々たれ」「何々しろ」と言うのが普通でしよう。すなわち(ambitious) で「あれ」と言ったのです。
では(ambitious)はどう言う定義があるかを調べます。これについてはOXFORD Advanced Learner’s DECTIONARY が下記の通りに具体的に記述しています。
(determined to be successful, rich, powerful, etc.)とあります。「大志」と言う言葉は、中国で生まれた言葉か、日本で生まれた言葉か、私は知りませんが(determined to be successful, rich, powerful)のように、はっきりとした定義が,あるのかもわかりません。
博士は、若い生徒たちに、諸君は日本の将来に役立つように、各々しっかり目標を決め、腰を据えて頑張れという、激励の言葉を送ったのです。私のような老人でも、頑張っているのだと言っています。当時の博士の年齢は50歳でありましたから(this old man)を老人と訳すのは適当ではないと思います。
(this old man)は(boys)に対する言葉であろうと思います。したがって、「私」とするのが最適です。
博士は日本の学生に接してみて、自分のアメリカの学生と比べると、大変真面目ではあるが、少々ガッツに物足りなさを、感じていたのではないでしょうか。生徒たちが英語で自分の思いを話すには、英語力が十分であったかどうかと言う事もあったでしょう。博士から見て、少々物足りないとの感じを持たれたのも致し方のないことではなかったのでしょうか。
「少年よ、…」と言う言葉は(boys, be ambitious)と言う言葉を翻訳したのではなく、別にあった言葉だったのではないかと考えています。
博士の言葉も、博士がこの言葉を発した当初から、有名であったわけではなかったそうですから、その「少年よ、大志を抱け」を広めた人物は、博士の言葉に「少年よ、・・・」をうまく乗せて、あたかも博士の言葉として広めた可能性があります。本人が意図していないことを、あたかも、本人が意図したかのように言い広めることは、問題でしょう。
さらに、志に大きい志、小さな志などと言うものはないと思います。例えば、小さい子に、大人になったら、何になりたいかと聞けば、例えば、学校の先生になりたいというかも知れません。大人から見れば、大きな望みではないように見えても、その子にとって先生になりたいと言う気持ちは、その子にとっての立派な「大志」です。
又、「少年よ、・・・」には(like this old man)が入っていません。意図的に、(like this old man)を外したものかどうかは不明ですが、大変大事な内容を抜かしています。
クラーク博士はご自身が、(being ambitious)であることを実践されてもおられたし、それを誇りにも思っておられたからこそ、( like this old man.)とわざわざ 言われたものと思います。(boys, be ambitious like this old man)は激励の言葉、「少年よ、大志を抱け」は訓示です。激励と訓示は全くの別物です。
以上の通り(boys, be ambition like this old man)訳が「少年よ、大志を抱け」と言うのは間違いです。 (10経E 平子 邦雄)
【近況報告】
今年(丑年)は、年女(還暦!)。さらに、厄年(本厄)、空亡(冬の旺)ときれいに三 拍子が揃いました。おまけに世界中で新型コロナのパンデミック。私の現世で最 大のターニングポイント?! そんな中、初孫が誕生。テレワークのおかげで、新米のパパとママが日中もそ ろって在宅、二人三脚の子育てです。あのマイペースな息子が、夜中に飛び起 きて粉ミルクを作り、朝から洗濯機をまわし、掃除機をかけている姿にびっくり、 にっこり。 また、気持ちは自粛しつつ(笑)、北海道から五島列島へ、日本再発見の旅が 続いています。先日は、新潟のワイナリー&オーベルジュ、山形の出羽三山へ。 国宝の五重塔まで雪道を歩き、斎館で精進料理をいただきました。 鎌倉のオフィスも駅前通り沿いへ移転、実業家だった茶人の家を趣きをなるべ く残しつつ改装、ピアノを置いた小さなイベントスペースもできました。 みなさまとご一緒させていただける日が近いことを願っています。 (27文A 柴崎由紀)
【この一年の雑感】 新型コロナウイルスに始まり、未だ先が見えない状況が続いています。 思いだすに、この一年なんと耳に馴染んだことのない言葉が多いか。 そのいくつかを書き出してみると、「あべのマスク」から始まり、「PCR 検査」「パンデミック」「エクモ」「自粛(書けま すか?)」「不要不急」「3密」「クラスター」「濃厚接触者」「ソーシャルデイスタンス」「ステーホーム」「テレワーク」「ア クリル板」「無観客試合」「医療崩壊」「変異株」「ワクチン」等々・・・・数え切れません。挙句の果て、マスク、消毒液 そして体温計まで品切れ状態。ほとほといやな事ばかりです。 一方、オリパラの延期(根拠もなく一年延期)、アメリカ大統領はトランプからバイデンに、日本も安部から菅(ガー スー?)に首相交代そして中国は「ワクチン外交」等々・・・・これまた数え切れません。 そんな折つい最近 NHK で、解剖学者の「養老孟司」(鎌倉在住)の飼い猫「まる」との生活ドキュメンタリーが放映さ れていました。観た方もいらっしゃると思いますが、大変興味深い内容でした。 その中で彼が語っていたことに、 「新型コロナウイルス関連で印象に 残った言葉の1つは、【不要不急】だった。この年齢(83 歳)の人は 非常事態であろうがなかろうが、家にこもって余り外に出ないし、出る必 要もない。今の人生自体が思えば、【不要不急】である。」 年寄りのひがみと言えばそれだけの事だけど、養老氏の言には同感で す。医療に携わっている皆さんは大変なご苦労とご努力をなさって、【不 要不急】どころか不眠不休の日々を過ごされていることに頭が下がりま す。 この様な雑感でなく、憂いなく過ごせる日が一日でも早く来るのを待ち わびる今日この頃です。 (10経B 岩佐 福之)
【近況報告】
湘南成城会の皆様お元気でしょうか?合唱団出身の中嶋タメです。コーラ ス好きの私にとって今回のコロナはさすがに堪えました。大学入学依頼こ んなに長い間歌わなかったのははじめてです。 とは言えこういう時、ストレス解消に役立ったのはテニスとゴルフです。 テニスは、横須賀ダイヤモンドテニスクラブで週一回のペースで楽しんい ます。私と同行ならビジターでプレー可能なのでご連絡下さい。 またゴルフは、関戸ご夫妻と月一回のペースで富士箱根カントリークラ ブに連れて行って頂いてます。スコアはまだまだですが、ベースボールグ リップに変えて指が痛く無くなり、スイングが楽しくなりました。いつも関戸 先輩のお車に同乗させて頂いているのですが、車中にて人生相談、株の 話など喋りっぱなしであっという間に到着してしまいます。 4月1日チェックメイトゴルフクラブにて湘南成城会ゴルフコンペが開催されます。久しぶりに皆さまとラウンド出来 るので楽しみにしています。 私は今62歳ですが、ゴルフは男女問わず高年齢でも楽しめるスポーツです。今から始めたいと思っている方是 非湘南成城会ゴルフクラブへご参加下さい。1番下手な私がサポート致します。 今回はこの辺で失礼致します。 (2法E 中嶋貴弘)
【日々のこと】 すっかり足腰が弱くなり、遠出をすることが出来なくなりました。それでも杖をたよりにトボトボヨチヨチ散歩していま す。今まで知らなかった小径が沢山あるもので、新しい家や、庭や、林を眺めながら歩くと色々な草花、木々の花 などを楽しくみることが出来ます。その中で一番は桜で、染井吉野、山桜、玉縄桜、しだれ桜など木によって色合い もいろいろあってなかなかの風情です。毎日同じ桜を見ながら散歩すると、一日一日桜の表情 が変わり楽しいものです。今日(4月5日)は桜もほとんど散り、我が家の食堂から見える花咲 地蔵さんの桜や裏山の山桜も風に吹かれて花ふぶきになっています。そんなことで、毎日2、 3キロが気晴らしと、軽い運動になる様です。そうそう前記の小径にミツマタの苗木が数本植 えて在って、並んで咲いているととてもキレイでした。こんなご時勢みなさま元気にお過ごし下 さい。 (8文E 大沼善一)
【成城学園第一グランドの桜】
学園に通われた方々な ら、春になると見事に咲 いた、グランドの脇を流 れる仙川沿いの桜並木 を憶えていることと思い ます。私が高校在学中、 川の護岸工事のために、 元々植わっていた桜の 木が何本も伐採されてし まうことになりました。な んとか並木の復元をと、 ボーイスカウトの高校生 を中心に有志が立ち上 がり、写真のチラシを作 って古新聞紙の回収を 続け苗木購入の資金集めに奮闘したのでした。同窓会の協力も得て、足かけ2年後、1967年の学園創立50周年 の文化祭で植樹祭が催され、当時の高垣寅次郎学園長もスコップを握り植樹してくださいました。 それから50年後の2017年、学園創立100周年の春、当時の古新聞集め中心メンバーにより、「50年目のお花 見会」が高校新校舎カフェテリアで開催されました。あいにく当日は、今年と違って桜の開花が遅れていて、肌寒い 中やっと一分咲きと言う状況でした。まだお花は少なくても、川べりに雄々しく太い幹が連なり、川面に長く伸びた 枝が満開になった時を想像して感慨深くゆっくり眺めながら会場に向かいました。集まった懐かしい仲間達は、当 時に思いをはせたり、近況を報告し合ったり、楽しく盛り上がったのでした。ところがその会の時にまたまた、「グラ ンドを人工芝に改修するので、桜が何本か伐採されるかもしれない…」という話を耳にしていました。それ以来、お 花見の季節になる度にグランドの桜はどうなっているのかしらと気 にはなりながらも、確認の機会が無く過ぎていました。 先日、昨年末に急逝された渡文明前学園理事長のお別れの会が 3月27日に学園で開催され、遠藤会長がご弔問されるとのことでし た。是非同行して、「ついでに桜も見てきたい!」と思ったのですが、 あいにくどうしても都合がつかなかったので、50年前のお話をして、 「どうか写真を撮ってきてください。」とお願いをしました。遠藤会長 のお話によると、グランドの工事の影響はほとんど無かったらしく、 ちょうど満開を迎えていて、写真のように綺麗に咲き誇っていたと 伺いとても嬉しく思いました。 コロナ渦、不要不急の外出はガマン、先の 見えないプレッシャーのなか、ことのほか桜 に魅せられた春です。 (16文D 相澤千春)




右が本人









